アーティストと職人
あるベーシストとお話ししていて「俺たちは職人だからさあ」と言われて驚いたことがあります。その人は長年にわたり有名歌手のバックをつとめていて、そんな人が「職人」と自分を呼ぶのがかなり意外だったからです。
似たような話をプロオケのトゥッティ奏者からも聞いたことがあります。プロとして楽器演奏したり歌を唄えば一般の目にはみんな芸術家ですが、業界の中の人にとってはもっと細かい区分があるようです。
たとえば仏語では芸術家はartiste、職人はartisanといってどちらもartを含んでおり地続きでとらえられています。地続きではあるけど別の単語ということは同じではないわけです。ではその違いはどこでしょうか?
ベーシストの例で言えば歌手の求めに応じて音を出すのがバックの役割です。トゥッティ奏者の例で言えばマエストロ(指揮者)の考えを理解してそれに合った音を出すのが役割です。演奏家が演奏技術を提供する役割に徹する時、それを「職人」と呼ぶように思います。
自分の表現を披露する人が芸術家であり、他人の求めに応じて専門技術を提供する人が職人と言えそうです。
では職人に芸術性が必要ないかというとそんなことはありません。マエストロの頭の中で鳴っている音を共有できないと、それに合う音を鳴らすことはできないからです。他人の芸術を理解してその良さを尊重できないと役割が果たせません。だから芸術性をそなえた職人である必要があります。
またアーティストと職人の立ち位置は変わるものでもあります。トゥッティ奏者もリペアマンの前ではアーティストです。言わずもがなリペアマンが職人の立ち位置になります。職人ではありますが芸術を理解してないと仕事にならないのは先の話とまったく同じ。演奏家の頭の中で鳴っている音を共有できないとリペアマンも良い仕事ができませんからね。
この点について知り合いの弦楽器職人さんと話していて彼は、木工の技術があれば楽器は作れるがそれだけでは楽器の調整はできないと言っていました。
木工をできれば弦楽器の形をした物が作れます。ここまでが1つ目の段階。
試行錯誤を経て、どこをどうすれば響きが増すのか、雑音が消えるのか、音色が変わるのか分かるようになります。材や加工法や構造と音の関係性という物理現象を理解し再現ができること、これが2つ目の段階です。技術としてはここまででも相当卓越しています。しかし調整はさらにその先ということでした。
調整は依頼主の感性が良しとする音を楽器から引き出す作業です。感性は人によって違います。そのため人それぞれ何を良しとするか理解しなければなりません。物理から感性へと橋渡ししてあげる必要があります。
この木工と楽器調整の話は鍼灸においても示唆的です。
安全に鍼を刺すことができれば学校の実技試験はパスすることができます。ここまでが1つ目の段階。
さらに鍼による刺激で体にどのような変化が起こるか理解し再現ができると、これが2つ目の段階です。しかしこれだけでは患者さんの求めにこたえることはできません。
施術では患者さんが感じる痛みや不快感に向き合う必要があります。感覚は共有することができません。できるのは想像力をはたらかせて理解に努めることだけです。しかし患者さんは感覚が変わって初めて良くなったことを実感します。そのような変化を出すために、2つ目の段階までの技術を使って適切に体の変化を引き出すこと、つまり体から感覚へと橋渡しできることが重要です。
残念ながら鍼灸では上に述べた2つ目の段階がすでにあいまいです。そもそも生きている人の体が相手なので100パーセントの再現性は望めません。しかしそれを差し引いても、患者さんが内的に感じている苦痛が共有できないためにどのような体の変化に着目すべきか分からないことが問題になっている気がします。
その結果起こりがちなのが、2つ目の段階をすっとばして人間性とか共感力に頼ることで3つ目の段階を乗り切るか、脈とか筋肉の緩みとかこちらの都合でピックアップした体の変化を根拠に3つ目の段階での効果を強弁するか、の二つです。
前者は技術がないただのいい人だし、後者は技術はあるけど向いている方向が見当違いです。
私の場合は音楽家の患者さんをみることが多いので実際の音や演奏動作の変化を求められます。人間性とか共感力だけでは何の役にも立ちません。またこちらの都合でピックアップした体の変化で将来の好転を強弁することもできません。
他方で音や指・唇の動きなど変化を共有しやすい悩みが相手であるため、2つ目の段階と3つ目の段階を行ったり来たり、評価・検証のサイクルが回しやすいといえます。
と、ここまで書いてきて自分が置かれた環境が実はとても恵まれたものであったことに気づきました。
最初から音楽家の患者さんをみることで、共有できない悩みを相手にすることは少なかったし、鍼で体が変化しても患者さんの悩みと無関係なこともあると早々に気づくことができました。私自身の能力というよりはそういう環境設定に育てられているのですね。
鍼灸師は他人に求められないと仕事になりません。その意味では明らかに職人の立ち位置です。そして患者さんの頭の中にある苦痛を理解できないと適切な仕事ができません。楽器職人とよく似ています。
音楽家が良い職人と出会えた時のわくわく感、安心感ってあるじゃないですか。患者さんにもそう思ってもらえるよう、私も頑張らないといけません。
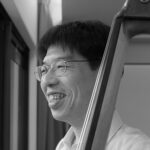
2016年、東京都練馬区の江古田にて音楽家専門の鍼灸治療院を始める。
2021年、東京都品川区の鍼灸院「はりきゅうルーム カポス」に移籍。音楽家専門の鍼灸を開拓し続ける。
はり師|きゅう師|アレクサンダー・テクニーク教師



