エールとコーダ ろう者と聴者、理解と自立のものがたり

年始に映画を2本観た。『エール!』(原題はLa Famille Bélier)と『CODA コーダ あいのうた』。両者は同じ内容でエールが原作、コーダはそのリメイクである。
4人家族の中で自分だけ耳が聞こえる女の子が歌の才能を見出され、本人も自分に自信を持てるようになり、最後は歌を学ぶために家を出るというお話。こう書くと単純だが実際観るとかなり泣ける、感動する映画だ。
ろう者とは比べるべくもないのだが私自身片耳が聞こえず、鍼灸師として突発性難聴の患者さんに施術することが多い。耳の問題界隈はなるべくフォローすることにしていて半ば課題として観始めたのだが、ラストに進むにつれ意味不明の感動におそわれてしまった。
この言葉にならない感動を言語化してみようと思う。なぜこの映画を観て人は感動するのか。
物語は聴覚障碍者の家族の中ただ1人健聴者の女の子を主人公として動いていく。両親と兄弟が1人(エールでは弟、コーダでは兄の設定)それに主人公の4人家族だが、彼女以外の3人は生まれつき耳が聞こえず、家庭内のコミュニケーションはすべて手話だ。映画の中では一切説明されていないがこのような生い立ちから、主人公は手話を母語として育ち、後で音声言語を獲得したことが推察できる。
こういう子どもをCODA(Children of Deaf Adults)と呼ぶ。リメイク版のタイトルであるコーダはここから来ている。
あまりよく知られていないことだが、手話は音声言語とはまったく違う一つの「言語」である。そのためCODAの子どもは聞こえる人の世界と聞こえない人の世界を幼いころから行き来することになる。別の言語、別の文化なのだから移民の子と似た境遇と言えば近いものが想像できるかも知れない。子供ながらに大人の役割を担わされることから、ヤングケアラーと通じる部分もある。
主人公も家族と外部との仲立ちを一手に担わされている。それはこの一家にとってなくてはならない役割だ。病院では両親と医者の間で通訳し、家業(エールでは酪農、コーダでは漁業)では取引先との交渉事は彼女の仕事である。忙しくて疲れているから授業中に居眠りしたり、あまり友達が多くなくやや孤立気味の学校生活だ。さらに家族の障碍や、(音声言語を後で覚えたせいか)自分の声や発音をネタにからかわれたりして自信を持てないでいる。
そんな主人公だが学校の授業で音楽の教師から歌の才能があると言われる。なんなら歌で進学したらどうか?そのためにレッスンしてもよい、とまで。本人も歌うことで新たな自分を発見し徐々に自信を持ち始める。そして先生の勧めにしたがって、エールではメトリーズ(ラジオ・フランス放送局の附属合唱団)、コーダではバークリー音大のオーディションを受けることを決意。
しかし自分の夢と家族内での自分の立ち位置を両立することは難しい。家族の中で唯一健聴者の自分がいなくなったら家業が切迫することは明らかだからだ。特にコーダでは当局の査察により、健聴者の乗船なしに漁船を出すことを禁止された状況である(エンジンの異音に気づかなかったことや無線が聞こえない状態での操船が危険と見なされた)。健聴者を雇う余裕なんかないから彼女が乗るしかない。
また自分の夢である歌を家族に理解してもらえないのもつらい。そもそも両親は歌を聞いたことがない。生まれつき難聴だから歌がどんなものかも知らないのだ(映画の設定ではこうだが、音楽を楽しむ難聴者も多いので、難聴=音楽を知らない、ではないことを補足しておく)。
結局、進学はあきらめて家に残ることを選ぶ。そんな中唯一の発表の機会となった学校の文化祭、娘の晴れ舞台に家族も参観することになった。耳の聞こえない一家はここで初めて彼女の歌に触れる。このシーン、途中から無音になる。映像だけが動き続けることで、映画の観客である我々も聴衆が涙し拍手する姿をただ「見る」ことになる。
ここから物語は怒涛の展開を見せ、主人公は家族全員の応援を受けて一度あきらめたオーディションに臨む(多分、願書を取り下げてなかったとかで受験できたのだろう)。居並ぶ試験官の前、彼女は声と手話両方で歌う。
ざっくりいうとこんなあらすじだ。
いろいろな見方があると思う。まずクライマックス。主人公がオーディションで声と手話両方で歌うシーン。
両親が聴覚障碍者ということは、彼女にとって最初に覚えた言葉が手話だったことを示唆する。ところが手話では家族以外とはコミュニケーションがとれない。それで第二言語として音声の言葉を獲得する。英語版のコーダでは発音をからかわれたことがあって人前で歌う自信がない、と言うくだりがあり、このあたりの複雑な事情を説明しているのだろう。
オーディションの会場には家族もいて、彼らに向けて手話しているのはもちろんだが、生まれ落ちて初めに与えられた言葉で表現していると見ると、このシーンはぐっとくるものがある。一番素直に自分を表現できる言葉でやっと歌うことができた、一人の人間が内面で抱えるいろいろな矛盾とすべて和解して受け入れた場面。こういう人の歌が響かないはずがない。
また、文化祭が終わって帰宅した後でお父さんと娘だけになり、もう一度歌ってくれないかと頼むシーン。お父さんにはもちろん聞こえるわけないのだが、娘の喉に手を当てて振動を感じ取ろうとする。理解したいという思いが痛いほど伝わってくる。
思えばこの映画全編においてやや説明不足なところがあり、観る側が理解に努めないと分からないような余白が残されている。手話のシーンもすべてに字幕があるわけではなく、最低限ストーリーが追えるようにつけられている。正直、今の手話はなにを話しているの?と思う場面がたびたびあった。
しかしふと思いいたる。聴覚障碍者が映画を観たら同じことを思うのだろうと。文化祭の場面でしばらく音を消す演出は、聞こえない世界を疑似体験させ、ちょっとした想像力を働かせてもらう意図なのだろう。
もちろんいくら想像しても完全に理解することはできない。では理解しようと努力することは無駄なのか?そんなことはない。このお父さんのように聞こえないのは百も承知で聞こうとする、分かりたいという思いとそのための営為はそれだけで尊い。
そして最後のシーン。エールではパリへ、コーダではボストンへと主人公が旅立つ。
英語版のコーダをもとに書きおこすと、ひとしきり家族全員で抱き合った後でお父さんが一言「Go(もう行け)」と娘にうながす。それに対して娘が返すのは手話で「I really love you(本当に愛してるからね)」。
聴覚障碍者のお父さんの声が聞けるのはおそらく全編でここ1か所だけ(コーダの脚本にはわざわざ太字で”He uses his voice”と書かれている)。また聴者の娘が手話だけで話す珍しいシーンになっている。声でうながす聴覚障碍のお父さんと手話で返す聴者の娘という見事な対比になっている。そしてこの手話には字幕の説明はない。アメリカ手話について調べないと分からない二人のやりとりだ。
ここは主人公がこれから一人立ちする場面であると同時に、残された家族もまた娘なしで自立しなければならない場面だ。お父さんの「Go(もう行け)」にその決意が感じ取れる。娘の自立は多分オーディションのシーンで完成しているのだが、それは家族を切り捨てずにまるごと受け入れた上での自立だ。だから別れに際して「I really love you(本当に愛してるからね)」と手話で返す。これ以上ないエンディングだと思う。
ところで本作品には多くの当事者が関わっている。まず仏語版エールの元になったシナリオは、ヴィクトリア・ドゥヴォスというフランスのコメディアンによって書かれたそうだ。彼女の父のアシスタントにCODAの方がいて、その人の話が元になっている。それを脚色して制作されたのが仏語版エール。だからお話のリアリティがそもそも高い。
それをさらにリメイクする形で制作されたのが英語版コーダだ。英語版コーダでは聴覚障碍者の役を聴覚障碍の役者が演じることでさらにリアリティを増している。誤解のないよう断っておくと、これは聴覚障碍のある素人を役者に起用したのではない。聴覚障碍があり手話で演劇するプロの役者を起用しているのである。米国演劇界の層の厚さ、人材がいかに多様かがうかがわれる。
巷にはエールとコーダを比較して優劣を語る論評が見られるが、私は比較することに意味はないと思う。エールがなければコーダはないし、ヴィクトリア・ドゥヴォスのシナリオがなければエールもまたない。
原案があまりにも素晴らしく、関わった人々がレスペクトしているのはそこだ。もちろん後から作った方が前作の伝わりづらかった部分を変えることができるので、より整理され焦点の合った脚本になっていると思う。しかし作り直しながらその時々で関わった人が知恵を出し良い作品が出来上がっていくプロセスそのものにこの作品の本質があるような気がする。
だから私はエールにもコーダにも等しく敬意を払いたい。素晴らしい作品を世に出してくれてありがとう。
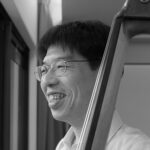
2016年、東京都練馬区の江古田にて音楽家専門の鍼灸治療院を始める。
2021年、東京都品川区の鍼灸院「はりきゅうルーム カポス」に移籍。音楽家専門の鍼灸を開拓し続ける。
はり師|きゅう師|アレクサンダー・テクニーク教師



