出来たのに出来なかったと思う罠
痛みが急に取れると多くの人はまだ痛いところがあるんじゃないかと思ってあれこれ試します。しかし「まだ少し痛む」と言う場合でもさっきより大きく動かせればそれは改善しています。あるいは「今度はこっちが痛い」と言う場合もさっきの痛みは取れたので一歩前進です。
演奏にまつわる不調の場合、なにをもって前進とするか判断の難しいことがあります。たとえばハリ施術後の試奏で一発目に出した音が思いどおりの良い音がして、しかしこの音の再現をねらって2回、3回と繰り返すと元に戻ってしまうことがあります。
この場合、最後に出た音の印象を持ち帰ると「やっぱりダメだった」という思いが残ります。そして施術後一発目の音が素晴らしかった事実を無視して全部ダメという評価になります。
楽音を出す行為は体の各部分の動きが絶妙に組み合わさって成立しています。必要な要素がうまくかみ合わないと音が出ません。つまりそもそも音が鳴る物理条件がすでに狭いことが多いのです(実際初心者には音出しすら困難が楽器は数多い)。言ってみれば1番から100番までの番号があるうち音が鳴るのはそのうちの一つしかないみたいな感じです。
唯一鳴る番号を例えば47番として、それ以外を全部無視するのはもったいない話です。仮に番号が47番に近いほど鳴る可能性が高いとしたら46番や48番に当たったら惜しいと思いませんか?それらをダメなデータとして切り捨てたら科学的な観察と分析ができません。科学的な観察と分析は再現性をもたらします。それのない実践はいつまでも運任せの博打です。
もう一つ着目したいポイントがあります。一度はうまくいったのに2回目、3回目が期待どおりでなかった時に全部をダメだと思ってしまう思考そのものです。ものごとをネガティブ寄りに評価する思考傾向が過ぎるとうまくいった事実まで無視する点でやはり科学から離れていきます。それと同時にうまくいくために必要な体の状態も無視してしまう気がします。
思考は体の動きにも影響すると考えています。例えば涙を流すとか鳥肌が立つといったことは自律神経系の働きです。普通は自分ではコントロールできません。ところが役者さんは意図的にこういうことができたりします。本当に悲しかったり寒かったりするわけではありません。そういう反応が起こるようなことを頭の中で思い浮かべるだけです。
体全体の筋肉の緊張状態は自律神経系がコントロールしていて、あらゆる動作はその条件のもとになされます。ということは役者さんのケースを考えれば、思考が自律神経系に影響し間接的に演奏動作にも影響します。「できなきゃいけない」とか「できて当たり前」のような自分を追い込む思考が演奏に与える影響が少なからずあると思うのです。だとすれば演奏時にどのような思考を取るかも演奏技術の一環として考えたいところです。
ハリ施術後一発目の音を出した思考と、2回目3回目の音を出した思考はなにが違ったのか。それを探ることにもハリをする意味があると考えています。
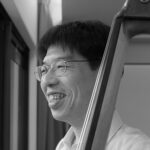
2016年、東京都練馬区の江古田にて音楽家専門の鍼灸治療院を始める。
2021年、東京都品川区の鍼灸院「はりきゅうルーム カポス」に移籍。音楽家専門の鍼灸を開拓し続ける。
はり師|きゅう師|アレクサンダー・テクニーク教師



