左右の指先の感覚を校正する話
尊敬する漫画家の大今良時さんが原稿の下描きを裏から描くという話をどこかのインタビュー記事で知りました。今さがしても元記事が見当たらず記憶が頼りですが、理由を2つほどあげていました。1つはアシスタントさんが先にペン入れしても下絵が消えないために(裏から光を当てて紙を透かして描いている)、2つ目はデッサンの狂いがすぐ分かるからです。
2つ目の理由は実際に絵を描いてみないとわかりづらいかもしれません。アンパンマンでもドラえもんでも鬼滅のキャラでもなんでもいいです。得意なものを描いてみましょう。そしてその紙をひっくり返してライトで透かして見ます。するとたいていの場合バランスが崩れていることに気づきます。大今さんの仕事を見たインタビュアーは驚愕し、自作(インタビュアーも漫画家)の英語版がアメリカで出たとき、(アメリカでは漫画も左開きになるため)左右反転された自分の絵の崩れっぷりを思い出してつらくなった、たしかそんな話でした。
反転させることは絵を描く人にとってよくある練習法のようです。しかしすべての原稿においてそうするのが普通というのはタダモノではありません。大今さん、すご過ぎます。
鍼灸師も左右差の補正が必要なときがあります。たとえば肩こりが右の方がひどいか左の方がひどいか触診で硬さをみるようなときです。このとき左右で指の感覚が違うと正当な比較ができません。
また両手が同じ感覚でないと患者さんの左右で同じ位置にとれないツボもあります。鍼灸師の中にはどちらか片手だけでツボをとるよう決めている人もいますが、その場合は皮膚のわりと表面的なところの感触で決めているように思います。整動鍼の場合は皮下の深いところでツボをとることもあり、角度や体勢の問題から片手ではとりきれません。そのため左右の指の感覚はできるだけ同じである必要があります。
しかし感覚の左右差は絵と違って一人では修正できません。品川のカポスに来てからは鍼灸師が複数いるので体を借りて指先の感覚を補正することができます。いや本当を言うと指先の感覚は結果でしかないので、そこに至る腕の使い方、頭の距離感、足の置き方なんかを微妙になおしています。体は日々変わっていくので、こういうことを調整できるのはありがたい環境ですね。
工場や研究機関では測定器がいつでも信頼に足る結果を出せるようにずれをなおすことを校正(こうせい)というそうです。指の感覚を補正する作業はまさにこの校正と言えます。
地味な取り組みの積み重ねですが、大今さんの高い画力も左右反転した下絵から来ていると思うとまだまだ手を抜けません。いえ、工場の測定器がずっと校正を必要とするように、この仕事を続ける限り取り組み続けることになるのでしょう。
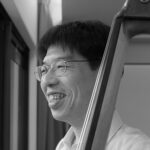
2016年、東京都練馬区の江古田にて音楽家専門の鍼灸治療院を始める。
2021年、東京都品川区の鍼灸院「はりきゅうルーム カポス」に移籍。音楽家専門の鍼灸を開拓し続ける。
はり師|きゅう師|アレクサンダー・テクニーク教師



